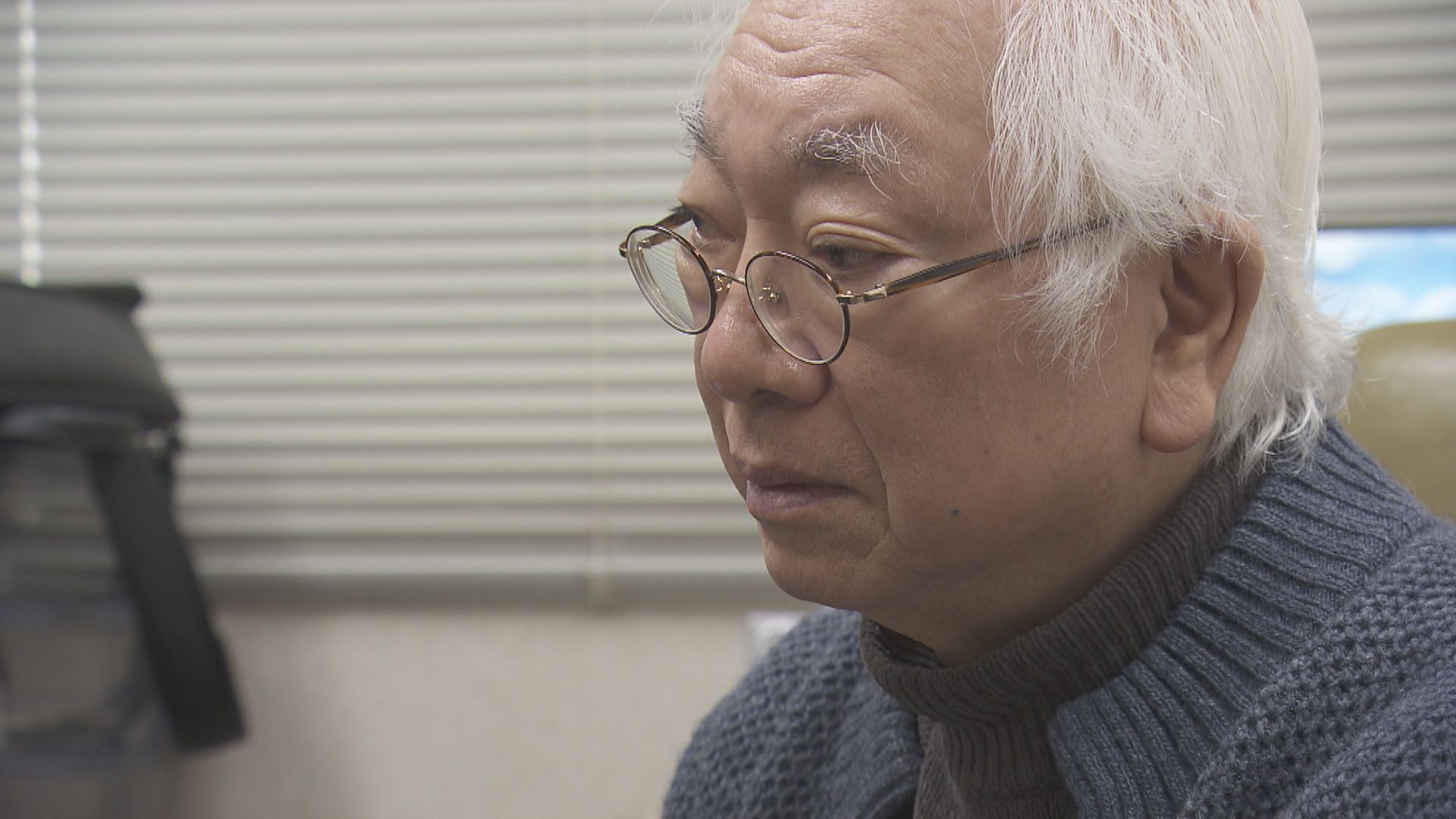いつの時代も若者たちの心をとらえ、ときめかせる"アイドル"。それは、あの長く苦しい戦争の時代も同じだった。当時、戦火のなかでも休むことなく幕を上げ続けた劇場「ムーラン・ルージュ新宿座」。"会いに行けるアイドル"に、出征する若者たちすら熱狂した。そんなアイドルたちもまた、慰問雑誌や戦地慰問、ブロマイド......さまざまな形で戦争に協力させられる。国策に絡め取られた戦時下のアイドルたちの足跡を追った。(取材・文:NHK特集ドラマ「アイドル」・「歴史探偵 "戦争とアイドル"」/写真提供:NHK)
菊池寛、志賀直哉、斎藤茂吉も夢中になった "会いに行けるアイドル"
 ドラマ撮影セット「ムーラン・ルージュ新宿座」の外観(提供:NHK特集ドラマ「アイドル」)
ドラマ撮影セット「ムーラン・ルージュ新宿座」の外観(提供:NHK特集ドラマ「アイドル」)ムーラン・ルージュ新宿座は1931年開業、今の新宿駅東南口付近にあった劇場だ。もとは映画館として作られた建物で、せまい舞台の前に430の客席が並ぶ。
学生時代、ムーラン・ルージュ新宿座に熱心に通った男性が、当時の情景を書き残している。
「ここは小じんまりした劇場で、ひいきのスターも近くで見られるし、また舞台からも、見物の中の見知りの顔がわかるらしく、目で挨拶したりする。(中略)せりふをトチって笑いが起っても、汚く野次る者は少なく、セリフを忘れ可成り無理なアドリブでつないでも、寛容な客は笑って之を許した」
本間正春『戦前の新宿 ムーラン・ルージュ』より
小劇場ならではの、舞台と客席との密接な距離感。現代でも一世を風靡(ふうび)した「会いに行けるアイドル」を彷彿(ほうふつ)とさせる。客席には学校帰りの学生や仕事帰りのサラリーマンがひしめき合い、さらには菊池寛や志賀直哉、斎藤茂吉といった著名な文化人の姿まであったという。
この劇場をプロデュースした支配人の佐々木千里は、「空気・飯・ムーラン!」というキャッチコピーを掲げていた。空気や食事のように、エンターテインメントもまた、人が生きていく上では欠かせないものだと提言したのだ。
出征する若者たちが絶叫した「明日待子バンザイ!」
ムーラン・ルージュ新宿座の公演は、終戦間際の1945年5月に劇場が空襲で焼失するまで続く。
戦時下、アイドルたちの活動は一体どのようなものだったのか。「元祖アイドル」ともあだ名される、ムーラン・ルージュ新宿座の元トップスター・明日待子さんのインタビューがNHKに残されている。
「ずーっとやっていた。一日も休みなし。B29が来ると『みんな劇場から出てください』って。そうしたらみんなお客様は出てね、その辺にある防空ごうへ入る。それでまた『空襲解除』って言うでしょ。そうするとみんな集まってくる。アリがおいしいものに集まってくるみたいに(笑)」

終戦の前年、1944年から東京への空襲が本格化すると、学徒出陣で出征を余儀なくされた若者たちが続々と劇場に現れるようになる。
「やっぱりやる方も一生懸命だったけど、見る方も一生懸命でね。『これは見納めだ』と思って見に来ているんですね。明日がどうなるか分からないって気持ちで。でもやっぱり娯楽を求めて来たんですね」
あるとき、そんな出征前の若者たちの行動に明日さんは驚かされた。
「客席で何か言ってるからその辺がざわめいている。何でそんなざわめいているかと思ったら『バンザイ!明日待子バンザイ!』ってね。私たちは演技し続けていかなければならないし、何が起こったんだか、その時は分からなかった。だから続けてました、そのまま」
出征してしまえばいつ命を落とすかも分からない。憧れのアイドルに二度と会うことはかなわないかもしれないーーそんな思いが若者たちを突き動かしたのだろうか。
戦争という緊急事態のなかでは"不要不急"のようにも思えるエンターテインメント。実際には、アイドルたちは戦争の時代においても、人々の不安に寄り添い、生きる希望を与える存在だった。
忘れられない「特攻隊のお兄ちゃまたちの澄んだ目」 女優・中村メイコさん
アイドルたちは、戦地の兵士たちを訪問し歌や踊りを披露する「戦地慰問」にも駆り出された。
2歳から映画やラジオの世界で活躍する女優・中村メイコさん(88)は、あるとき軍の関係者から前線の将兵たちへの慰問を依頼され、行き先も告げられずにあちこちを訪れた。なかでも忘れられないのは、10歳くらいの時に慰問したという特攻隊の若者たちの姿だ。

「小さい子どもを見ると皆さんすぐ涙ぐんで。『メイコちゃん、じゃあ、お兄ちゃんたちは行きます』って言って、みんな飛び立っていらっしゃいましたね。特攻隊の兵隊さんたちに『行ってまいります』っていう言葉はないんですって。つまり、行って帰ってくるってことはなくて、そのことがわかって出陣する。
(終戦から77年がたつ今でも)悲しみは変わりませんね。あの澄んだ目をしたすてきなお兄ちゃまたちが、みんな戦争のために『行きます』って言って、それっきり帰ってこない。亡くなられたんだっていうことは、私の人生の中で、やっぱりすごく大きなショックというか打撃として残ってますね」
 海軍特攻慰問に訪れた中村さん(上段中央)
海軍特攻慰問に訪れた中村さん(上段中央)なぜ子どもだった自分が特攻隊の若者のもとへ送られたのか。中村さんは後年になってその意味を考えるようになった。
「この小さな子どもたちのために僕たちは潔く命をささげるんだっていうのが、きっと当時の兵隊さんたちにとって、一番の納得感があったんでしょうね。子どもを見ることによって、この子たちの未来のために自分たちは犠牲になるんだ、この子たちの良い明日があるように、僕たちは我慢して飛んで行くんだっていう。それが死につながることだったんですけど。でも、その材料にちょっと使われたかなと思うのも正直な気持ちですね」
アイドル写真に添えられた 兵士たちへの"ラブレター"
中央大学経済研究所客員研究員・押田信子さんは、戦時中に発行された「慰問雑誌」を研究している。そこから、戦争の時代のアイドルが担わされた役割が見えてくるという。
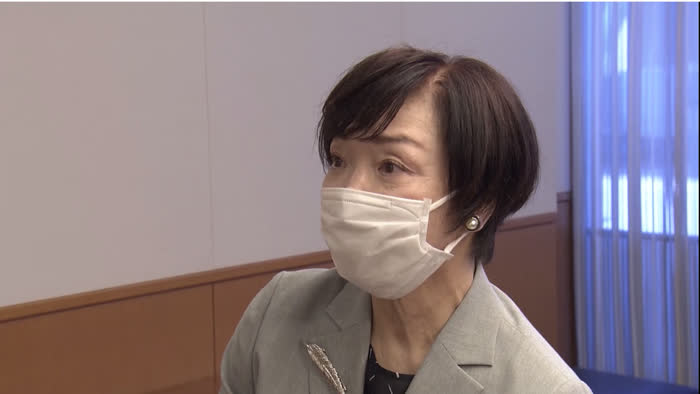
「慰問雑誌」とは当時、戦地で戦う将兵のために特別に作られた雑誌だ。制作自体は委託を受けた出版社がおこなっていたが、その発行には陸軍・海軍が自ら関わっていた。
雑誌を開くと、当時の人気女優や歌手たちの笑顔が目に飛び込んでくる。押田さんが注目するのは、アイドルたちの写真に添えられていた「慰問文」だ。たとえば、日中戦争開始の翌年、昭和13年に発行された慰問雑誌には、日本軍の輝かしい戦果を称賛する女性たちが並び、兵士らの健康を気遣う恋人のような言葉も添えられている。
 資料提供:押田信子さん
資料提供:押田信子さん「わたしたちは、今日の歓びを迎へて、何といってお礼を申上げてよいやら、分かりません。ただもう、ぢっとしてをれない感激に、熱い涙を覚えるばかりでございます」(高杉早苗)
「お元気でますます御奮戦のことと拝察いたします。戦地は私どもには想像もつかない厳寒がつづくとか、何か御不自由はございませんか。(中略)どうぞ何なりと仰しやって下さいませ」(橘公子)
『戦線文庫』3号(1938年11月)より
アイドルたちの美しい写真と慰問文は前線の兵士たちから絶大な支持を集め、編集部には新たな写真を求める声が殺到した。こうした慰問文は、編集者などが女優の姿を借りて書いたものだった可能性があると押田さんは指摘する。
「慰問文は、(写真にうつる)この方たちが戦地の兵士に向けて書いているスタイルを取っている。ただ、よく読んでみると、これをつくっていた編集者やコピーライターが書いてるんじゃないかというのが透けて見える文章なんです。例えば陸軍の慰問雑誌『陣中倶楽部』は、大日本雄弁会講談社(現在の講談社)が編集していました。つながりのある作家がたくさんいますので、かなり泣かせどころを心得ている作家が書いたんじゃないかなって思ったりしますね」
泥沼化する戦争を継続するため 放たれた"異性の爆弾"
 資料提供:押田信子さん
資料提供:押田信子さん軍が慰問雑誌を前線の将兵たちに供給した狙いを、押田さんはこう分析する。
「軍部としては、やはり戦力が落ちるのが一番怖い。戦力が落ちないために、どうしたらいいのかと。なにしろ兵士たちは若い青年。彼らの心を一番つかむこと、それがアイドルの写真だったり、娯楽です。
兵士は常に戦ってるイメージがあるじゃないですか。ところが、戦闘がない間は案外暇だったわけです。暇なときってトーンダウンするじゃないですか。自分たちは何のために戦い、未来はどうなるんだと思うんです。そうすると戦力は落ちていきますよ。彼らに疑問を持たせないため、ある意味ではモルヒネのように、嫌なことを忘れさせるような意味もあったかと思います。要するに、"異性の爆弾"ですよね」
慰問文はアイドルのイメージを利用しながら、戦争に関わるさまざまなメッセージを広く伝達しようとしていた。それが明確に表れているのが、不足する金属の供出を求める慰問文だ。
「腕輪、首飾り、バックル、ブローチ、凡(およ)そ金と名のつくものは、みなまとめて箱にしまいました。(中略)指輪があった時より、わたしの指はずっと美しいのです。人は、うわべのかざりでは美しくならないということを、わたしはハッキリ知りました。何だか今度の事変にお礼を言いたいような気持ちにさえなりました」(草笛美子)
※旧仮名づかいを改めました
一枚のブロマイドでさえ利用された戦争
戦時中に若い将兵から絶大な人気を誇った女優・高峰秀子さんは、戦後につづったエッセーで複雑な心情を吐露している。彼女のブロマイドは慰問品として戦地へ大量に送られ、多くの将兵の手に渡った。
「中国大陸に散った無数の私のブロマイドは、日本の兵士たちに鉄砲の下をくぐる勇気を与えたのか、あるいは祖国への郷愁、母や恋人や姉妹への恋慕をつのらせたのか、私は知らないけれど、一枚のブロマイドでさえ、戦争に利用されたという事実は忘れることが出来ない」
高峰秀子『わたしの渡世日記』より
慰問雑誌や戦地慰問、そしてブロマイド。さまざまな形で戦争に巻き込まれていったアイドルたち。彼女たちが担ってきた役割は、ある面では「戦争協力」と呼べる行為でもある。
 ドラマ撮影セット「ムーラン・ルージュ新宿座」の劇場内(提供:NHK特集ドラマ「アイドル」)
ドラマ撮影セット「ムーラン・ルージュ新宿座」の劇場内(提供:NHK特集ドラマ「アイドル」)押田さんは、「当時のアイドルたちもまた、複雑な立場に置かれていた」と話す。
「お国のため、兵士さんのためになるなら、やろうという気持ちだったんじゃないでしょうか。批判的な気持ちも、もちろんあったでしょう。しかし、それが許される時代ではなかったですからね。ましてや彼女たちは、大衆を相手にしているわけですよね。大衆の支持を得てこその仕事なわけですね。時代が戦争に傾いていき、自分を応援していた青年たちが戦地に行った。だったらば、やっぱり応援していこうという気持ちだったんじゃないでしょうか。そうですね、ちょっと切ないですね」
アイドルたちの思いと、アイドルに憧れ、勇気や元気を受け取る若者たち。その双方の思いが国策に絡め取られたのが、当時の「戦争とアイドル」の歴史だったのではないだろうか。
ーーー
この記事は、NHKが特集ドラマ「アイドル(外部リンク)」(8月11日放送)、「歴史探偵 "戦争とアイドル"(外部リンク)」(8月10日放送)の番組制作にあたり独自で取材・調査した内容をもとに制作したものです。