


被爆した元少年兵の今聞くべき生の声です
太平洋戦争末期。航空機による特攻が連日報道される中、世間に知られることなく展開された特攻部隊がありました。広島の暁部隊。そこにはボートによる特攻訓練をする少年兵がいました。元少年兵は「爆弾を積んで夜襲をかけた。1名1艦。みんな戦死だもん」と語ります。しかし、命を失う覚悟を決めた彼らを待ち受けていたのは、"特攻"ではなく"原爆"でした。戦後79年。多くの元少年兵が90代半ばを迎え、取材を受けることが難しくなる中、岩手県に住む男性が取材に応じてくれました。元少年兵「(ピカッと光った瞬間に)皮膚が焼けたからギャーワーもうすごかった。『兵隊さん助けて助けて』って。とてもとても...」。元少年兵の見たものとは...
岩手県遠野市。日本の原風景が残るのどかな町。「遠野物語」で知られる民話のふるさととしても有名です。そんな町で生まれ育った伊藤宣夫さん、96歳。「軍人でなければ男ではない」と教育されていた時代。戦局が悪化し、本土決戦が叫ばれはじめると、少年たちは我先にと軍人を志願しました。伊藤さんも戦局が悪化した1945年2月、16歳で陸軍特別幹部候補生に志願。広島の暁部隊に配属となります。
 左:陸軍特幹生公募ポスター(江戸東京博物館所蔵)、右:伊藤宣夫さん17歳(千田国民小学校で撮影)
左:陸軍特幹生公募ポスター(江戸東京博物館所蔵)、右:伊藤宣夫さん17歳(千田国民小学校で撮影)伊藤さん「その当時、4カ月ごとに少年を募集し、特攻訓練をやったんだ。だから私もこれに行くと思っていた」「爆弾を積んで夜襲をかけた。1名1艦。そこまでいったんだよ...。みんな戦死、戦死だもん...」
全長約5.6mのベニヤ製のボートに爆雷を積んで敵艦に突っ込む。太平洋戦争末期、陸軍が秘密裏に開発した小型ボートで特攻攻撃が行われていたといいます。「マルレ」と呼ばれたこの特攻艇を操縦していたのは、陸軍船舶司令部、通称「暁部隊」に所属していた10代の少年兵たちでした。
 マルレと特攻部隊の少年兵6人 台湾で撮影(「㋹の戦史‐陸軍水上特攻の記録‐」より 提供:奥本剛)
マルレと特攻部隊の少年兵6人 台湾で撮影(「㋹の戦史‐陸軍水上特攻の記録‐」より 提供:奥本剛)少年特攻兵たちは広島県江田島市の海で訓練を行っていました。沖縄やフィリピンなどに派遣された1期生は2288人中1636人が戦死したのです。
同期の多くが特攻兵として広島県江田島市などに向かいましたが、伊藤さんは違いました。
伊藤さん「私は通信兵になって、香川県の小豆島から広島市の宇品に来るときに暁16710部隊陸軍船舶通信補充隊に転属になった」
北は樺太から南は沖縄までの広範囲から1000人近くが入隊した中で、通信兵に転属されたのは160人。伊藤さんは、広島市で苛烈な訓練に励む日々を過ごしました。通信兵だったため特攻に向かうことなく、8月6日を広島で迎えることになったのです。
あの日、17歳だった伊藤さんは爆心地から4.5km、暁部隊の司令部や特攻部隊をまとめる船舶練習部が置かれた広島市の宇品港で被爆。
空襲警報が解除され、電報を持って防空壕から飛び出て海岸沿いを走っていた時でした。
「『ピカッドーン』と鳴った。その『ピカッ』となった時に外に出ている人たちはみんな皮膚が焼けたのよ、光で。『ギャー』『ワー』もうすごかった」
とっさに防空壕に飛び込み難を逃れました。
 きのこ雲と防空壕の前でたたずむ伊藤さんが描かれた紙芝居の絵
きのこ雲と防空壕の前でたたずむ伊藤さんが描かれた紙芝居の絵伊藤さん「防空壕から出てみたら、もやがかかっていた。だんだんそれが暗くなってきて土砂降りの雨が降ってきた。それが黒い雨。30分以上は降った」
雨が上がると、すぐに原子雲があらわれたといいます。
伊藤さん「にょっきり上がって、ゆっくりとモックモクモックモク、上がっていったんですよ。800mか600m上がったところで、今度はきのこの形になって広がった。そして、夕方3時か4時ころになって消えていった」
暁部隊は爆心地から離れていたので被害は少なく、広島の中で唯一軍隊としての機能を保つことができたため、被災者の救護活動にあたったのです。
「(江田島で特攻訓練していた部隊は)原爆が落ちた日の午後に宇品に上がってきた。上陸用舟艇で。そして救護活動にあたった」
「一生懸命この人たち(負傷者)を何とかしなくてはと思って。みんな『兵隊さん助けて』と。負傷者はみんな両腕を前に出して皮膚が焼けただれた状態だった」
 皮膚が焼けただれた被爆者が描かれた紙芝居の絵
皮膚が焼けただれた被爆者が描かれた紙芝居の絵夜、広島駅の北側にある二葉山に行くよう命じられた伊藤さんは、移動中に市内の惨状を目にしたといいます。
「(爆心地から)2.5kmの範囲内は火の海だった。(建物の)下敷きになってそのまま焼かれた。生きたまま焼かれたわけだから。それが青い炎で燃え上がった」
いくつか渡った橋の上も凄惨な状況でした。
「(やけどをした人で)足の踏み場もないくらいいっぱいです。『兵隊さん助けて助けて』って。『水をください』って。『水、水』って言うんだけど、何もできなかった」
「そして足にすがったりするんだもんね。とってもかわいそうで見てられない。だから『班長殿、戦争は止めた方がいいですね』と言ったな」
 青い炎が上がる市内と橋の上の惨状を描いた紙芝居の絵
青い炎が上がる市内と橋の上の惨状を描いた紙芝居の絵同じ通信補充隊の同期160人のほとんどは、爆心地から1.7kmの千田国民学校にいました。伊藤さんは生き残った同期から、「原爆がピカッとなったとき160人ほとんど飛ばされた」と聞きました。そして、倒壊した建物の下敷きになった戦友は「生きたまま互いに手を振り笑って死んでいった」といいます。
「そのときは仕方ないんだなと思って...。原爆で亡くなる...。やっぱり生きててもらいたかったなとは思いますけどね...。みなさんはよかったんだ。戦争のない時に生まれて」
伊藤さんの紡ぐ言葉には、悲しみともあきらめとも怒りともとれる、複雑な感情が垣間見えました。
 原爆で亡くなった戦友を思う伊藤さんの表情
原爆で亡くなった戦友を思う伊藤さんの表情1945年9月に復員命令が出て地元の遠野に戻った伊藤さん。
「私が『おばんでございます』と言ったら、入り口に寝てた姉と子どもが出て、びっくりして『あやぁ宣夫帰ってきたやぁ』って。それからみんな起きてきて。みんな喜んで。よかったよかったって」
被爆による差別もありませんでした。
「遠野では被爆者がどうとかこうとかっていうことはなかった。だから大いに私は話をした。よくほかで広島にいてどうとかこうとかって言われるけど、何もなかった」
人に求められれば被爆体験を話してきたといいます。10年前には知人がその体験をまとめた紙芝居を作ってくれました。
「被爆証言は、平和と命の大切さということで、地元の小学校で毎年11月と12月にやっている。今は高齢になって6年生だけ。毎年やらなければならないと思い、できるだけ残していきたいなとがんばっていました」
2016年8月6日に行われた平和記念式典では、広島市の松井一実市長が読み上げる平和宣言に伊藤さんの被爆体験が盛り込まれました。
2016年 広島の平和宣言(一部抜粋)
「当時17歳の男性は『真っ黒の焼死体が道路を塞(ふさ)ぎ、異臭が鼻を衝(つ)き、見渡す限り火の海の広島は生き地獄でした。』と語ります」
「おかげさまでここまで生きてきました。96歳。数えで97歳になる。もう少しで、3年で100歳。本当に私は幸せだった」
伊藤さんの被爆証言はいつも詩吟で幕を閉じます。
「ヒロシマや 地獄の街の 青い炎よ 平和の道を この紙芝居」
日本を守ろうと17歳で特攻隊に志願した伊藤さんは、広島で戦争の悲惨さをいやというほど実感しました。この体験を後世に残していかなければならないと強く思ったといいます。
「核兵器を廃絶し、願わくば、世界人類が平和で豊かな世界でありますように。その到来を切に念願してやまない」
 詩吟を披露する伊藤さん
詩吟を披露する伊藤さん

古武家朋哉
広島ホームテレビ報道部 記者96歳という年齢を感じさせないくらいよく話す伊藤さん。耳は聞こえづらく足元もおぼつかなくなってきているとはいえ、盛岡冷麺を1人前たいらげるほど元気でパワフルな方でした。
伊藤さんは常々「私は運がよかった」と話します。暁部隊の少年兵には建物の下敷きになって亡くなったり、救護活動による入市被爆で命を落としたりした人も多くいます。
「戦争も核兵器も絶対にあってはならない」
"特攻"と"原爆"、人間が生み出した殺戮兵器の恐ろしさを身をもって体験した人だからこそ言える力強さが、その言葉に込められているように感じました。

長崎で消えた町"2秒の伝言"残した男性の正体が明らかに 「似とるね...」息子の涙 #きおくをつなごう #戦争の記憶
NBC長崎放送
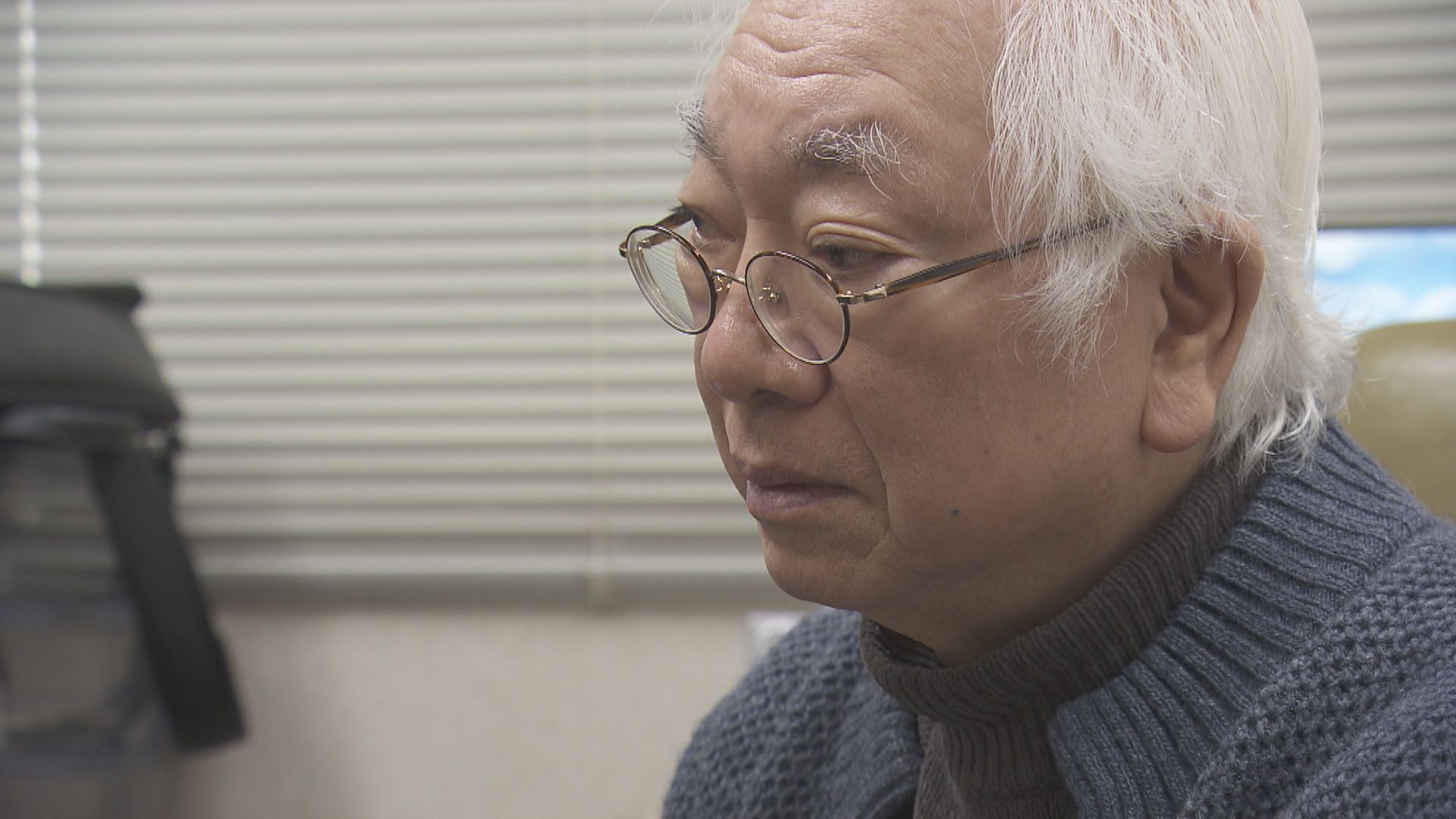
「見つかったのは弟のあごの骨だけ」家族4人を原爆に奪われた医師 失意のなか治療もやけど患者に消毒しかできず 「映像の医師は父」名乗り出た息子 #きおくをつなごう #戦争の記憶
RCC中国放送

全身が「赤鬼」のようだった 18歳で被爆し大けが、原爆症に苦しみ「死にたい」と思った日々も 俳優・水上恒司さんがたどる #戦争の記憶
KTNテレビ長崎

「おんぶの男の子は私」3歳で被爆、名乗り出た男性 "一生の病"と傷跡抱え 語り出した家族の記憶 #きおくをつなごう #戦争の記憶
RCC中国放送

「父はBC級戦犯で絞首刑に」存在を隠して生きた息子 唯一のつながりは処刑前の「8通の遺書」 #戦争の記憶
毎日放送

「私の体の中に毒針がいる」79年経った今も続く被爆者の苦悩 #戦争の記憶
TSSテレビ新広島